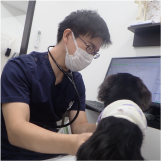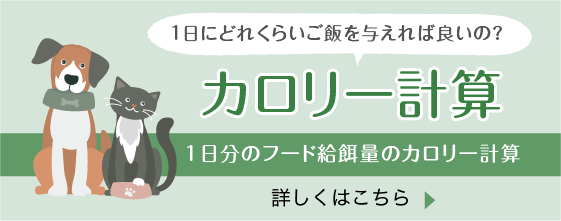動物病院で抗ガン剤治療を勧められた 怖いけどどうしよう?
抗がん剤と聞いて良いイメージが湧かない方はとても多いのではないでしょうか?
自分の家の子に抗がん剤なんて、、、どんどん弱っていってしまうのでは?
よけいに辛い思いをさせるだけなのではないか?
なんて考えが頭の中を巡ってしまって悩んでいらっしゃる方を多くみてきました。そこで、今回は抗がん剤治療について少し解説したいと思います。
分子標的薬やメトロノーム療法といった比較的新しい治療法に関してはまた、解説する機会を設けられればと思いますので、今回は割愛しています。
抗ガン剤とは
がんに対する治療方法として外科手術、放射線治療、化学療法が3大療法といわれており、化学療法がいわゆる抗がん剤治療にあたります。
外科手術や放射線治療はがんができた部分を局所的にターゲットとした治療法であるのに対し、抗がん剤治療は注射や内服で全身に投与する治療法になります。全身の腫瘍細胞に対して一気に治療できる反面、しこりができている部分などに局所的に高濃度に効果をだす治療ではないので、抗がん剤治療ではしこりを小さくするほどの効果は見込めないことが多くなります。
人医療では抗がん剤治療でも完治を目指して、副反応が出る前提で高用量の抗がん剤投与を実施することもありますが、それとは異なり、犬猫での抗がん剤治療では完治を目指すというよりもQOL(生活の質)を維持することを目標とすることが多くなります。
その分、ほとんどの場合通院での治療が可能ですし、よくイメージされるような強い副反応が出ることは少なく、「本当に抗がん剤治療中?」と思われるような状態で生活を送れている子が多いと思います。
抗ガン剤を使用するケース
前述した通り、抗がん剤は全身に作用させる治療法となるため、全身性の腫瘍(リンパ腫、白血病)や診断時にリンパ節や肺への転移がみられる腫瘍、手術をしても今後転移を起こす可能性が高い腫瘍などの場合に適応となり、腫瘍の縮小や増殖の抑制が期待されます。
腫瘍の種類にもよりますが抗がん剤で腫瘍を完治できることは稀で、寛解(腫瘍が目には見えないぐらいに小さくなっている状態)にさせたり、進行を抑制したりすることで動物のQOLをあげる、もしくは維持することを目標とすることが多い治療となります。
しかし、動物に対する抗がん剤治療は人医療に比べ情報が非常に少なく、効果的な抗がん剤がわかっていないがんが多いのも事実です。抗がん剤治療の際には、メリット/デメリットなどをしっかりと獣医師と相談したうえで実施していくこととなります。
副反応はないの?
がん細胞は他の正常な細胞と比べて活発に(異常に)増殖しているのが特徴です。
一般的な抗がん剤治療では、そのような活発に増殖している細胞に対して治療効果を発揮します。しかし、常日頃から新陳代謝が活発で増殖を繰り返している毛根、消化管粘膜、骨髄(免疫細胞である白血球などを作っている)などに対しても傷害作用を示してしまいます。
そのため、よくある副反応として、脱毛、嘔吐下痢・食欲低下などの消化器症状、好中球(白血球のひとつ)数減少や血小板数減少のような骨髄抑制が見られることがあります。
脱毛に関しては、毛質の変化やひげの脱毛などが見られる場合がありますが、目立つほどの重度な脱毛は起こらないので問題になることはほとんどありません。
多くの子では消化器症状も示しませんが、2−3割の症例で一過性の嘔吐や食欲低下がみられることがあります。入院が必要なほどの強い症状を示すことはさほど多くありません。
骨髄抑制は重度になれば、細菌に対する抵抗力が低下することで敗血症に至り、発熱して体調の悪化が急激に見られます。そのため、抗がん剤投与中は血液検査を定期的に実施して好中球数が減りすぎていないか確認する必要があります。
また、薬剤によっては血尿や便秘、肺炎などその薬特有の副反応というものもあるため、獣医師からきちんと説明を受けて予防/対応するようにしてください。
概して、犬猫での抗がん剤治療では、入院治療が必要なほどの副反応は5%程度になるような薬の量での投与が基本となっています。
がんを完治させることは難しいかもしれませんが、副反応のないQOLの高い生活を送れることを目指す治療といえます。それでも、最近のいくつかの報告では軽度の副反応が出るぐらいの抗がん剤の投与量の方ががんに対する治療効果は高いことも示されており、副反応がでない〜ごく軽度の副反応が出るぐらいの微妙な調節の抗がん剤投与が理想といえるのかもしれません。
ご家族へのご協力
上述してきたように、獣医領で行われる抗がん剤治療は世間的にイメージされているほどのつらい治療にはならないことが多いですが、正常細胞にも障害を与え得る毒薬や劇薬を使用していく治療であることに変わりはありません。
そのため、普段使用されるような抗生物質や痛み止めなどに比べると副反応を引き起こす割合が少し多くなってしまいます。しかし、それぞれの薬剤における副反応の出かたやタイミングなどはわかっていることが多く、事前にそのタイミングにあわせて制吐剤や抗生物質、整腸剤などを使用することで辛い状況を予防することが可能です。
そのような予防的な薬剤は飲み薬で処方することも多いので、その点はご自宅でご家族にご協力いただくようになります。
また、定期的な血液検査を実施して好中球数や血小板数の確認を実施することが多いですが、ご自宅でも可能であれば毎日体温測定を実施していただくことで敗血症などの重篤な症状にいち早く気付くことができます。
「体温測ると発熱はあるけど、元気・食欲はある」この状態であれば、すぐに受診していただくことで、もしも入院治療などが必要だとしても、短期間で済ませることができます。
多くの抗がん剤では、注射薬を院内で投与することが多いですが、薬の種類によっては飲み薬を処方することがあります。
抗がん剤は、正常な細胞にも作用してしまうとお伝えしましたが、薬剤への接触や吸引などで飼い主様たちにも影響が出る可能性があります。
動物に出した薬だから人には影響ない、なんてことはありません!そのため、飲み薬で処方された場合には、できる限り素手では触れない、分割などは行わない、嘔吐物や排泄物には注意するなどご家族の身体への影響も考慮しなくてはいけません。
妊婦さんや乳幼児、ご高齢者などがご在宅の状況では、治療効果と一緒にリスクなどもよく検討した上で抗がん剤治療の実施を獣医師と相談してください。
投与後の注意点
抗がん剤投与後は数日で嘔吐や下痢などの消化器症状、1週間前後で好中球数減少などが見られることが多いので、体調の変化には注意してあげてください。
また、薬剤の種類にもよりますが、便や尿などの排泄物に微量とはいえ抗がん剤(毒薬や劇薬のことが多いです)の成分が残っている可能性があります。そのため、抗がん剤投与2−3日は排泄物に直接触れる、吸引するなどしないように、マスクやグローブをつけて処理し、ビニール袋を二重にして廃棄するなどの工夫をしてください。
愛するペットに抗がん剤治療をするかどうか、、、その判断を迫られていること自体が非常に辛い状況に置かれていることになりますが、そんな時こそ病気の進行具合、今後起こりうる状況、治療効果などをどうか冷静に判断していただけるようにと切に願います。
方針を決めるのにゆっくりと考える時間は少ないかもしれませんが、納得いくまで獣医師や看護師にもご相談ください。
この記事を書いた人