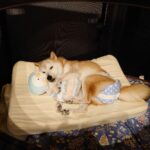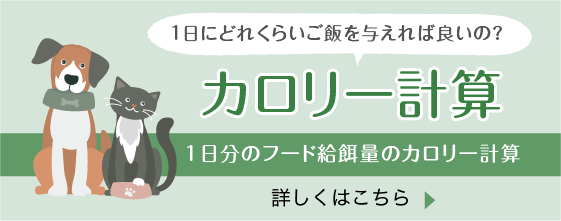犬と猫も認知症になります ~犬と猫の認知機能低下についてご家族が知っておきたいこと~
認知症とは
「認知機能不全症候群」のことを略して認知症と呼んでいます。脳の障害や様々な原因により認知機能が低下して日常生活に支障が出てしまう状態のことです。
ペットの高齢化に伴い、犬猫の認知症もよく見かけるようになりました。
認知症が起こりやすくなる年齢やよく見られる症状、治療法、予防法などを説明していきます。
認知症が起こりやすい年齢
犬の場合、年齢でいうと7歳からシニアといわれています。シニアになると認知症の症状が出始め、年齢が上がるにつれて認知症を発症する確率は上がっていきます。
アメリカで実施された調査によれば11歳~12歳の犬のおよそ30%、13歳になると急増し、15歳~16歳の犬のおよそ70%、猫では11~14歳の約 8%、15歳以上の約50%認知症を示唆する症状がみられるといわれています。
認知症の原因
認知症の原因は、脳の萎縮や異常なタンパク質の蓄積、ストレス、後天的な脳の障害(脳梗塞や脳腫瘍、脳炎、血管変性)、神経細胞(ニューロン)の消失によるものと言われています。
しかしながら、原因を特定することは難しく、詳細は今のところわかっていません。
日本で認知症と診断される犬のうち80%近くが柴犬であったという報告があり、遺伝的なものが関係しているのではないかと考えられています。
認知症の症状
これらの症状が、初めは「なんとなく」であるものが、徐々に進行していきます。
症状の頭文字をとってDISHAAと呼んでいます。その他にもVISHDAAとまとめているものもありますが、今回はDISHAAでまとめてみました。
認知症の診断
認知症の診断ははっきりとは確立されていません。しかし、その症状から診断に役立つチェックシートを使い、指標として用いられています。
犬や猫の場合は人間のように自覚症状を訴えることや、会話をすることによって認知症に気付くことがないため、ご家族がいかに様子の変化に気付くか、よく観察しているかが認知症を診断するヒントとなります。
また一見すると認知症のような症状でも他に病気が原因であることもあるため、様子の異変に気付いたら、受診するようにしましょう。
また、認知症と思ってしまいそうな病気との鑑別も必要です。犬の甲状腺機能低下症、脳腫瘍や前庭障害、白内障、猫の腎臓病、甲状腺機能亢進症等は、高齢の犬猫で多く見られる病気であり、一見すると認知症と似た様子が見られることがあります。
また、認知症との鑑別が難しい病気として、行動学的疾患(分離不安症、常同障害)でも徘徊や夜鳴きが見られることがあります。
認知症の治療
現在認知症を治す治療薬はありません。認知症のケアは症状の進行をゆっくりにすること、問題となる行動を和らげることがメインとなってきます。
認知症の予防や初期症状においては生活習慣や生活環境の改善を行い、抗酸化作用のあるDHAやEPAなどのオメガ脂肪酸、ビタミンE・C、βカロテン、フラボノイドなど多くを含むサプリメントや食事を与えるといいでしょう。
昼夜逆転や夜鳴きなどで飼い主様の生活に支障がでる場合には、日向ぼっこをしたり日中に運動することで夜間眠りやすくしてあげたり、抗不安薬や鎮静薬を使用するという選択肢もあります。
認知症の予防
認知症の予防には、脳に刺激を与えることが重要と考えられています。たとえば、お散歩のコースを少し変えてみる、お散歩の時間を変えてみるといつもと違うものが目に入ってきて良い刺激になります。
頭を使うトレーニングも良いとされています。例えば、好きなおやつを隠して見つけ出して食べるといった「ノーズワーク」は10分間で1時間分の刺激になると言われています。
お顔やだけではなく、手足、指先を優しくマッサージすることも良いとされています。声をかけながら優しく触れたり撫でるなどスキンシップを取るだけでも効果が期待できそうです。
いくら予防しても、認知症にならないとは言い切れません。もし、認知症になってしまったら、介助や介護が必要になってきます。
その方法についてはぜひこちらをご一読ください。
この記事を書いた人