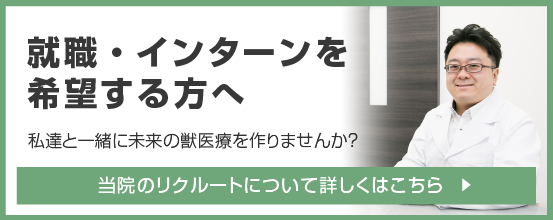犬のレッグ・ペルテス病
当院で実施した外科症例について紹介します。
今回は犬のレッグ・ペルテス病(レッグ・カルベ・ペルテス病、無菌性大腿骨頭壊死症)の症例です。
※術中写真が表示されますので苦手な方はご注意ください。
プロフィール
犬 トイプードル 避妊雌 7か月齢
来院理由
2、3週間前から時折右後肢挙上
既往歴
なし
検査
来院時右後肢挙上あり
触診にて右股関節伸展時疼痛あり、右後肢筋肉量低下
レントゲン検査にて右大腿骨骨頭の透過性亢進が認められる

診断
レッグ・ペルテス病
外科手術
レッグ・ペルテス病の治療として右骨頭切除術を実施
麻酔導入後、神経ブロック(仙尾椎麻酔)実施

毛刈りして消毒後切皮し、筋肉を分離して大腿骨頭を露出

骨頸部で切断、骨頭を切除

切除後、分離した筋肉を縫合し、皮下組織・皮膚縫合実施

手術後の経過
術後2日後退院、術創問題ないため2週間後に抜糸
術後のリハビリに関しては炎症を抑える、筋肉のケアを中心に起立補助、重心移動を行い可能な範囲で屈伸運動実施
その後も自宅でのリハビリを継続し、術後8か月で筋肉量差は残るものの歩行時後肢挙上ほぼ認められず
レッグ・ペルテス病について
レッグ・ペルテス病は主に成長期の小型犬にみられ、後肢の大腿骨の一部である大腿骨頭の血流が阻害されて壊死を引き起こす病気です。血流阻害の原因については明らかとなっていませんが、ホルモンの影響、遺伝的因子、解剖学的形態、関節を形成する関節包内圧、大腿骨頭の梗塞などに関連していると考えられています。通常片側性に起こりますが10~17%の症例で両側性に生じることもあります。

壊死によって大腿骨頭がもろくなると、後肢特に股関節に痛みが生じ、足を庇うような歩行が見られます。徐々に悪化すると足を地面に着くことを嫌がり挙上します。すると足を使わなくなるため筋肉量が落ちていきます。
身体検査では股関節の痛み特に後ろに伸ばした時に痛みを感じる、関節可動域の減少、筋肉量低下などがみられます。
X線検査では大腿骨頭や骨頸部の変形、虫食い状に透過性亢進などがみられます。早期ではX線検査だけでは異常を検出できず、この場合はCT検査が有用です。
治療は抗炎症薬による内科治療や運動制限などによって疼痛の軽減がされることもありますが、ほとんどの犬では痛みを取り除くために壊死がみられる骨頭を切除する外科的治療が必要になります。この外科的な治療が今回紹介した大腿骨頭切除術になります。
術後は患肢を使用するようリハビリを実施することが重要で、術後早い段階から行うことで足の機能の回復を目指します。
術後の機能回復のためにも筋肉量が落ちすぎないよう早期の外科手術が望ましいです。そのため歩行に違和感がある、足を痛がるなどがある時は動物病院にご相談ください。